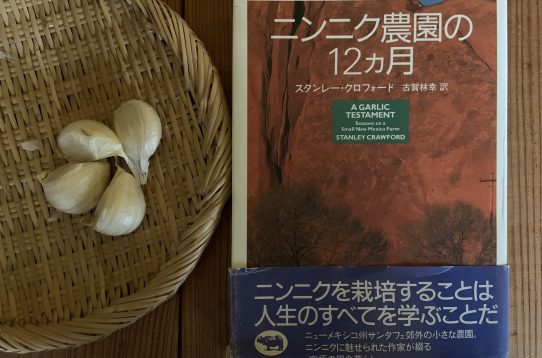「カントク」と初めて会ったのはいつだったのか、まったく思い出せない。多分、10年以上は経ってるだろう。誰か共通の友達の部屋か、なにかのパーティか。そんなところだ。
それ以来、真夜中のバーや、一転、快晴の小笠原の海なんかで、なんどもばったり会ってきた。会うといつも、「おぐらん。久しぶり」と言って、ニヤッと笑う。初めて会った時も、多分、あの笑顔で挨拶を交わしたのだろう。だから仲良くなった。仲良くなったとは言っても、二人で飲みに言ったこともないし、連絡を取り合うわけでもない。心を開きあったというのが正しいのかもしれない。
「カントク」と出会う前から、彼の作品は観ていた。『ポルノスター』、『青い春』、『ナインソウルズ』。大好きな阪本順治監督作品にも通じる、錆びた鉄の味がする映画だったからだ。
10代後半から、暴力の匂いがする街をふらつくのが好きだった。特に、新宿がしっくりきた。歌舞伎町、ゴールデン街、大久保までつながるラブホテル街。酒が飲めるようになると、一癖も二癖もあるような常連で埋まっているバーに行っては、そこらの芸術家気取りの大人たちに食ってかかっていた。何者でもない自分への苛立ちを辺り構わず撒き散らした。ベロベロになって歩いた、あの頃の真夜中の新宿には、紛れもなく錆びた鉄の味がした。
「カントク」が本を出版したとは聞いていた。昨日、たまたま渋谷のジュンク堂へ野口種苗のタネを見に行った。次の打ち合わせまでまだ時間があったので、ゆっくりと店内を歩いていたら、ばったりこの本と出会った。『おぐらん、久しぶり」と言われた気がして手に取った。
「素晴らしい映画は感情が震え、その振動がいつまでも続いた。揺さぶられた感情は振り子のように揺れ、回り、焦がして、痕跡を残して消えていく。永遠に消えない、腕に彫った名前のように心に刻まれた。その痕跡を魂という人もいる。あの感情を味わいたくて、もっと知りたくて、見たくて、心を震わせたくて、儲からない映画を撮り続けている。百年先まで辺りに漂っているような、遠い過去から未来まで走り抜けるような。一周の閃光のような、美しい痕跡を」
豊田利晃『半分、生きた』(HeHe刊)の前書きを読んで、一瞬で引き込まれた。
「カントク」とは、なんども会っているが、お互いの身の上話なんかしたこともない。会えば、酒を酌み交わして、くだらない話をして「くっく」と笑いあって別れる。だから、この本を読んで、阪本順治監督の『王手』の脚本をまだ20歳そこそこだった「カントク」が書いたと知ってビックリした。
この本ではそんな「カントク」が自身がカントクした作品という時間の流れを軸に、映画について、仲間の役者たちについて、世間を騒がせた何度かの逮捕劇についてなどが、恐ろしく研ぎ澄まされた言葉で書かれている。
どの章も書き出しがいい。
「人生に勝ち負けは必要だ。」(『アンチェイン』より)
「いつも気づくと手遅れになっている」(『青い春』より)
「いつも何かひとつ足りない」(『ナインソウルズ』より)
「世界を真っ白に戻したい」(『モンスターズクラブ』より)
「人には船に乗る理由がある」(『プラネティスト」より)
「人間の一生は自分が描いた地図の上を歩くようには進まない」(『狼煙が呼ぶ』より)
豊田作品のファンがいたら、この書き出しこそ、それぞれの映画の本質だということに気づくだろう。不良は余分なことは言わない。一発で仕留める。
あっという間に読み終えた。気持ちが昂揚した。そして、「カントク」の物語の続きを読むように、自然ともう一冊の本に手が伸びた。もうずっと前に古本屋で手に入れてから、大切にしてきた本だ。
『クリームソーダの伴ちゃん』山崎眞行著(私家版)。
「商品のデザインは、男女両方が着られるようにした。
ロゴマークは『ドクロマーク』ー何にも束縛されない無法者の海賊たちのシンボルーに変わっていた。
キャッチコピーは、ジェームスディーンの「TOO FAST TO LIVE TOO YOUNG TO DIE」だ。」
(『クリームソーダの伴ちゃん』より)
ピンクドラゴンのゴッドファーザー、山崎さんが、相棒だった伴さんの死に臨んで書いた、おそらく関係者だけに配られたメモリアルブックだ。
「伴ちゃんは痛み止めのモルヒネを打たない様に医師に告げ、痛みと戦っていた。
一度も尿瓶を使わず、「オレには小さすぎる」と冗談を言いながら、死の一時間前、気力で立ってトイレに行っていた。
死が凄いスピードで迫ってきた。
看護婦さんが、シーツに一滴の血を見付けた。
看護婦さんと目が合った伴ちゃんは、自分の唇に人差し指をクロスさせた。
まだこんな時でも、伴ちゃんの美学は続いていた。」(『クリームソーダの伴ちゃん』より)
山崎さんとは、一度だけお会いしたことがある。それも、真夜中のバーだった。お酒を飲めない山崎さんは、コカコーラを何本もおかわりしながら、僕の話に付き合ってくれた。日本全国をドクロに染めた山崎さんは静謐な人だった。そして、少し照れた様にニヤッと笑って時折、自分のことを話してくれる。やりたいこととやれないことの間に挟まった様な気になって息苦しくてしょうがない思いを告げると、静かに僕の目を見て「自分がやりたい様に、それを思いっきりやることだよ」と言ってくれた。そして、続けて「きっと、やりたいことを思いっきりやったら、世間は嫌がります。そうなったら、こっちのもの。もっともっと嫌がられる様なことをやったらいいんですよ。そうしたらね、それを喜んでくれる仲間ができるから」と言った。
「悲しみをロマンティックにしたら終わりだ」(『クリームソーダの伴ちゃん』より)
最近、どこの街を歩いても錆びた鉄の味はしなくなった。その代わり、饐えたような腐敗臭ばかりが漂っている。かつての中国に「一掴一掌血(いっかくいっしょうけつ)」という言葉がある。それは、一度掴んだら、血の手形がつくくらい掴み、絶対に離すなという意味の言葉だ。
「カントク」は映画を。山崎さんは「ロックンロール」を。そして僕はアーバンファーミングを掴んだ。
錆びた鉄の味が恋しくなったら、自分の血の手形を舐めるしかない。